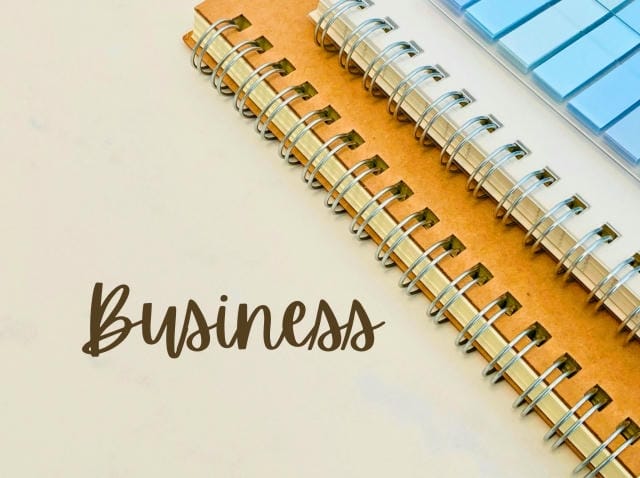産業の現場では、制御システムや設備の稼働状況を監視・管理するために情報技術の活用が広がっている。これらの監視・制御システムは、生産ラインやエネルギー施設など、社会や経済の基盤となるさまざまな場所で不可欠な存在となっている。これらのシステムを総称して、運用技術と呼ぶ。高度な自動化や遠隔管理、データ収集技術の導入によって、運用技術はかつてよりも効率的かつ強固なインフラ運用に貢献しているが、その一方でセキュリティの重要性も急速に高まっている。運用技術は電力、ガス、水道、交通、製造など、社会の根幹を成すさまざまな分野を支えるインフラに深く関連している。
こうした現場の制御システムや監視システムは、稼働情報のフィードバックや制御信号の伝達のために、専用のネットワークや機器を利用している。このため、従来は外部からの脅威とは無縁と考えられてきた側面があったが、情報技術の進歩とともに、オープンな通信規格や汎用技術が導入されるようになり、外部との接点も増加している。その結果、サイバー攻撃の対象となる可能性が高まり、インフラの安全確保にはセキュリティ対策が不可欠となっている。運用技術のセキュリティは、情報システムのセキュリティとは異なる要件や配慮が必要である。情報システムの領域では機密性や完全性、可用性といった三大要素を中心に対策が講じられているが、運用技術の場合は人命や安全、現実世界への直接的な影響力が極めて大きい。
たとえば、発電所や鉄道、浄水場などのインフラがサイバー攻撃にさらされて稼働停止や誤動作を起こせば、地域社会や国全体に深刻な被害が生じる恐れがある。そのため、システム停止や情報漏洩のみならず、施設の持続的な運転維持や物理的な事故防止までを含めて総合的に管理しなければならない。インフラに使われる運用技術のセキュリティを高める取り組みとしては、まずシステム資産の可視化が重要となる。関係する機器やネットワーク、端末がどこにどのように配置されているのかというインベントリ管理を行い、セキュリティ上の脆弱性や未許可のアクセスポイントを特定する。さらに、運用技術に特有のプロトコルや機材ごとの弱点を把握し、パッチ管理やアクセス制御など技術的な対策を徹底することが求められる。
また、従来は閉じた専用ネットワークで構築されていた運用技術環境でも、遠隔監視や自動化機能が強化され、業務の効率化が進んだ反面、インターネットとの接続機会が飛躍的に増えている。これに伴い、外部からの不正侵入や信号の傍受、マルウェア混入など、かつては想定しづらかった脅威への警戒が重要課題となっている。たとえば、操作端末や制御装置ごとにアクセス権限を最小限にとどめたり、多要素認証や物理的なセキュリティ対策を導入したりするなど、人為的・技術的な両面から堅牢な防御を構築する必要がある。一方で、運用技術の現場では、新しいセキュリティ対策を導入することが容易とは限らない。生産現場やインフラ施設においては、連続的な運転や24時間体制の監視が重視されており、システム構成の変更や一時的な停止は業務へ重大な悪影響を及ぼす可能性が高い。
そのため、既存の運用技術機器の寿命を前提としつつ、段階的かつ慎重にセキュリティ対策を適用する必要がある。教育や訓練も重要なポイントである。実際の現場では運用技術の担当者が最新のセキュリティリスクを理解し、インシデント発生時の対応手順や役割分担を定めておかなければならない。計画的な訓練や復旧シナリオの策定、外部専門家との連携を含めた体制強化は、運用技術を守るための大切な施策として注目されている。システムを越えた関係者同士の協力や情報共有もまた、インフラ全体の安全性向上に欠かせない。
国内外とも運用技術へのサイバー攻撃は増加傾向にある。標的型攻撃をはじめ、ランサムウェアや遠隔操作ウイルス、データ漏洩など、インフラへの被害が続発している現状を背景に、多くの国や関係機関がガイドラインや基準の整備を進めている。自治体や組織単位で監査や自己点検を積極的に実施し、多層的な対策の見直しや強化が推奨されている。今後は運用技術のインフラと情報システムの連携がさらに進み、従来以上に複雑で高度な管理体制が求められる状況が続くだろう。運用技術特有の特性やインフラとしての使命を踏まえつつ、長期的かつ全体的な視点からセキュリティ施策を立案することが、社会や産業を守る土台となる。
その取り組みは単なるシステム保護にとどまらず、持続可能なインフラ運営ひいては豊かな未来を目指すうえでも、極めて重要な意味を持っている。産業現場で活用される運用技術(OT)は、制御システムや設備の監視・管理を担い、電力・ガス・水道・交通・製造など社会インフラの根幹を支えている。近年は情報技術の進展により、運用技術にも汎用の通信規格やネットワークが導入され、効率化と高度な自動化が進む一方で、外部との接点が増加したことでサイバー攻撃のリスクも高まっている。情報システムと比較し、運用技術のセキュリティでは、機密性・完全性・可用性に加え、人命や安全、社会への影響など現実世界への重大なリスクが伴うため、被害が発生した際の影響範囲も広大である。そのため、単なる情報漏洩やシステム停止の防止にとどまらず、施設運転の維持や物理的事故防止も視野に入れた多層的な対策が必要である。
具体的には資産の可視化や脆弱性管理、アクセス制御、ネットワーク監視、最小権限の設定、物理的セキュリティの強化などを段階的かつ継続的に行うことが求められる。運用現場ではシステム更新が難しいことから、既存機器を活かしつつ慎重な対応も重要である。また、担当者の教育や訓練、インシデント対応体制の整備、情報共有といった人的・組織的な取り組みも不可欠である。今後はインフラの複雑化や情報システムとの融合が進む中、社会全体の安全・持続可能性のために、長期的で全体的な視点に立ったセキュリティ対策の強化が一層重要となる。